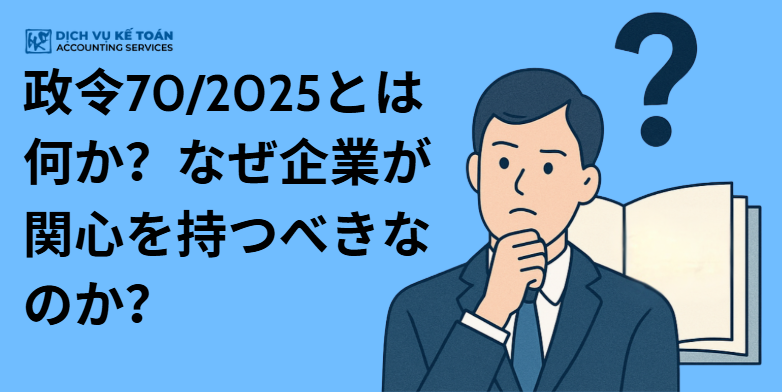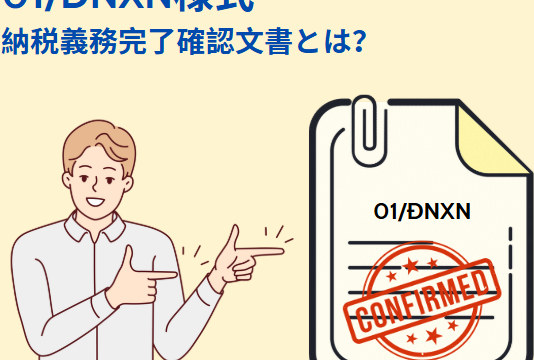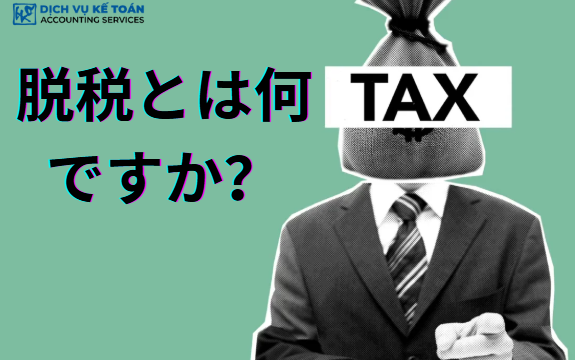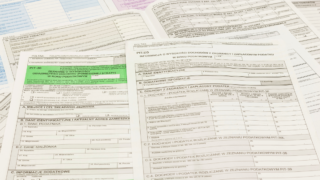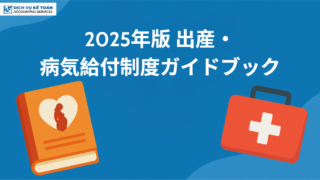ベトナムの政令70/2025の全体像を解説。インボイス、社会保険、現金支払、給与に関する主要な変更点と、日系企業が取るべきコンプライアンス遵守の解決策を詳述します。
政令70/2025が施行され、ベトナムの事業環境は一変しました。本稿では、電子インボイス、事業主の社会保険、非現金決済、給与の透明性に関する新規定の全体像を網羅的に解説します。
正式に施行されて以来、政令70/2025号はベトナムのビジネス環境に深遠な再構築をもたらしています。もはや草案や未来の予測ではなく、インボイス、社会保険、現金決済、給与管理に関する新規定は、すべての企業が直面しなければならない「現実」となりました。本稿では、その全体像を鳥瞰し、核心となる変更点をAからZまで詳細に分析するとともに、企業が法規を遵守するだけでなく、この挑戦を新たな競争優位性へと転換させるための戦略的解決策を提示いたします。
政令70/2025号とは何か?なぜ企業は注目しなければならないのか?
政令70/2025/NĐ-CP号(以下、政令70/2025号)は、ベトナム政府によって公布された極めて重要な法的文書であり、税務管理の近代化と事業活動の透明化に向けた政府の断固たる一歩を示すものです。これは単なる通常のアップデートではなく、インボイス詐欺の防止、国家歳入損失の撲滅、経済取引の標準化に焦点を当てた、体系的な大改革と位置づけられています。
政令70/2025号が完全に施行された現時点において、すべての企業がこれに注目せざるを得ない理由は、企業の存続に関わる4つの柱、すなわち「キャッシュフロー」「コスト」「業務プロセス」「リスク管理」に直接的な影響を及ぼすからです。これらの規則を軽視、あるいは適応を遅らせることは、高額な行政罰に繋がるだけでなく、事業活動そのものを停滞させ、競争上の優位性を失う結果を招きかねません。本政令は、大企業から零細企業に至るまで、例外なく全ての事業者に適用され、その各条文は深い管理上の含意を持ち、経営者自身の思考様式の変革を要求しています。政令70/2025号を深く理解することは、もはや選択肢ではなく、ベトナム市場で生き残り、成長するための必須要件となっています。
政令70/2025号における主要な4つの核心的変更点の詳細分析
政令70/2025号は、主に4つの領域を中心に構成されており、それぞれが企業の即時対応を必要とする革命的な新規定を含んでいます。
1. インボイスに関して:規定の厳格化と100%の透明性への指向
第一に、小売インボイスへの情報記載が厳格化されました。スーパーマーケット、レストラン、コンビニエンスストアといった消費者向け直接販売を行う事業者にとって、購入者情報を記載しない、あるいは複数の取引を一枚のインボイスにまとめる、といった慣行は、法規を遵守する上ではもはや不可能となります。新規定は、購入者からの要求があった場合、その身元を特定する情報(氏名、住所、個人納税者番号等)を完全かつ正確に記載することを義務付けています。これは、不正なインボイスの売買を防止し、消費者の権利を保護することを目的としています。
第二に、税務当局とデータ連携するレジスターの使用義務範囲が拡大されました。旅客輸送、飲食サービス、ホテル業、小売業など、現金取引が多い業種は、全ての売上データをリアルタイムで税務当局のシステムに直接送信することが義務付けられます。これは単なる設備投資の問題ではなく、未記帳収入の余地をなくす、収益管理の哲学そのものの変革を意味します。
第三に、最も重要な点として、誤謬処理プロセスが極めて厳格化されました。一度発行され、買主に送信された電子インボイスに誤りが見つかった場合、「インボイスのキャンセル」という概念は事実上廃止されます。代わりに、「調整インボイス」または「代替インボイス」の発行、あるいは様式04/SS-HĐĐTによる説明報告書の提出といった、定められた手順でのみ処理が可能です。これにより、全ての取引に「消せない監査証跡」が残ることになり、経理担当者には初回発行時からほぼ完璧な正確性が求められます。
2. 社会保険(BHXH)に関して:対象者の拡大と企業のコンプライアンスコストの増大
- 私営企業の事業主
- 個人が所有する一人有限責任会社の社長または総社長
- 事業世帯の世帯主(事業登録を行っている世帯が対象)
従来、これらの事業形態の所有者が、コストを最適化するために自身の名前を給与台帳に記載しないという慣行が広く見られました。しかし、新規定はこの「グレーゾーン」を完全に撤廃します。法の目的は、経営者自身の長期的な社会保障(年金、疾病、産休等)の権利を確保すると同時に、他の労働者との公平性を創出することにあります。
企業への直接的な影響:
- 固定費の増加: 企業は、上記の対象者のために、法で定められた基準所得に基づき、毎月社会保険料を納付する義務を負います。これは、財務計画に織り込むべき新たな固定費の発生を意味します。
- 申告・管理義務の発生: 経理・人事部門は、対象者の加入手続き、被保険者数の増加報告、そして毎月の保険料の申告・納付を速やかに行う必要があります。納付遅延には高率の延滞利息が課されるため、注意が必要です。
これは遵守必須の規定であり、経営者はコスト管理の考え方を変え、社会保険料の納付を自己の将来への投資として捉えることが求められます。
3. 現金に関して:非現金決済に関する「革命的」な規定
仕入インボイスは、その金額の多寡にかかわらず、VATの仕入税額控除およびCIT計算上の損金算入の適用を受けるためには、非現金決済(銀行振込等)の証明書が必須となる。
この規定は、従来の「2,000万ドン以上」という閾値を完全に撤廃し、企業間取引における現金決済を税務上、事実上無価値なものとします。政府の狙いは明確です。企業セクターにおける現金取引を根絶し、銀行システムを通じて全ての金融フローを100%可視化し、架空取引による経費の水増しを防ぐことにあります。しかし、企業側から見れば、これはオペレーション上の巨大な挑戦です。少額の仕入れにも現金が使えなくなり、支払方針を全面的に見直し、全ての企業間取引に銀行振込を義務付けるという、極めて厳格な内部統制の構築が必要となります。
4. 給与に関して:Etax Mobileアプリによる「二重給与台帳」の終焉
これにより、従業員は誰でも、自身の電子身分証明アカウント(VNEID)でログインし、会社が自分に対して公式に申告している給与額を簡単に確認できるようになります。これは、長年の慣行であった「二重の給与台帳」(社会保険料や税金を低く抑えるための低い公式給与と、残りを現金で支払う非公式給与)という行為を、極めてリスクの高いものに変えます。従業員が差異を発見した場合、企業はPITおよび社会保険料の追徴課税、さらには関連する高額な罰金に直面することになります。この規定は、企業に対し、総人件費(税金・社会保険料を含む)という真の労働コストと向き合うことを強制するものです。

政令70/2025号が企業の構造と運営に与える影響
上記の変更点により、政令70/2025号は、経理部門のみならず、企業全体の構造と運営方法そのものを変革します。
- 財務面: コンプライアンスコストが急増します。テクノロジー(ソフトウェア、レジスター)、人件費(全額申告される給与・社会保険料)、そしてコンサルティングサービスへの投資が必要となります。
- オペレーション面: 社内プロセスは標準化・厳格化されなければなりません。販売、購買、支払、給与計算といった全ての業務フローは、100%のコンプライアンスを確保するために再設計される必要があります。
- テクノロジー面: デジタルトランスフォーメーション(DX)が必須となります。税務当局と連携できない、統合されていない個別のソフトウェアシステムを維持することは、致命的な弱点となります。
- 戦略面: ビジネスにおける「グレーゾーン」は大幅に縮小されます。非公式な手段によるコスト最適化に依存したビジネスモデルは、もはや持続可能ではありません。企業は、真の経営効率と製品・サービスの品質といった、本源的な競争力で競うことを余儀なくされます。
企業が政令70/2025号を適切かつ効果的に遵守するための包括的解決策
この新たな法的環境に巧みに適応し、成長を遂げるためには、企業は戦略的かつ体系的なアプローチを取る必要があります。
1. 財務・経理プロセスの全面的な見直しと再構築
2. テクノロジーへの投資:コンプライアンス自動化の鍵
3. 人材育成と透明性の高い文化の構築
4. 専門コンサルティング会社の活用による安全なロードマップの策定
政令70/2025号は、ベトナムのビジネスの土俵そのものを、より透明で、近代的で、公正なものへと再定義する、真の革命です。適応の初期段階では、多くの困難とコスト圧力が伴うことは間違いありません。しかし、長期的な視野を持ち、変化に積極的に適応し、コンプライアンスを企業文化の一部と見なし、テクノロジーと人材への投資を体系的に行う企業は、この挑戦を乗り越えるだけでなく、新たな時代において飛躍し、その地位を確立し、持続的な成長を遂げる好機を見出すことができるでしょう。
ご不明点がございましたら、すぐにWacontre会計サービスにご連絡ください。ホットライン: (028) 3820 1213 またはメール: info@wacontre.com にて、迅速かつ丁寧にサポートいたします。経験豊富なスタッフが、お客様に対し、熱意をもって最適なサービスを提供いたします。(日本のお客様はホットライン (050) 5534 5505 にお問い合わせください。)